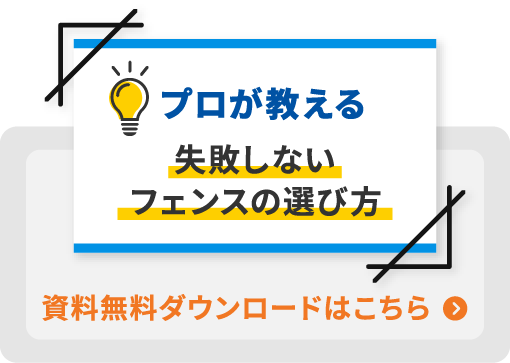![]() 2021.11.09
2021.11.09
お役立ちコラム 太陽光
太陽光パネルの素材について【徹底解説】

更新日:2023/03/01
みなさん、こんにちは。
久野商事株式会社の久野でございます。
最近、電気代が高騰した影響により、太陽光発電システムの導入を検討する企業や家庭が増えています。
よくあるお問合せ内容として、太陽光発電システムを始めた場合、製品の選定基準をどのようにすればいいのか相談いただくことが増えています。
特に太陽光パネルはメーカーだけでなく、利用されている素材によって発電効率が変わります。
そこで今回は太陽光パネルに使用されている素材である、太陽光電池の違いとそれぞれの特徴について説明していきます。
目次
太陽光電池の素材について
はじめに太陽光電池で利用されている各素材の紹介と特徴について説明していきます。
シリコン系
シリコン系は現在の太陽光電池でもっとも利用されています。
また、シリコン系の中でも主に単結晶、多結晶、微結晶、非晶質シリコンの4種類に分類されます。
①単結晶シリコン
単結晶シリコンは、高純度のシリコンの事を指します。
結晶粒が非常に大きく、高い効率で太陽光を変換することができるため、少ない太陽光パネルで効率良く発電することができます。
しかし、製造コストが高いため、他のシリコン系と比べて価格が高くなります。
②多結晶シリコン
多結晶シリコンは、単結晶シリコンよりも低純度のシリコンから作られているため、結晶粒が小さく変換効率はやや低くなります。
しかし、単結晶シリコンと比べて、製造コストが安いため、販売価格は安価となります。
主に産業用太陽光発電システムで利用されます。
③微結晶シリコン
微結晶シリコンは、非常に薄いシリコン膜を基板上に形成し、非晶質シリコンと結晶質シリコンを混ぜたシリコンで、単結晶シリコン製造時にできた端材や不良品を利用して作られているため、非常に安価になります。
変換効率は多結晶シリコンに近く、薄膜で作られるため、柔軟性に優れた太陽光発電パネルに使用されます。
④非晶質シリコン
非晶質シリコンはアモルファスシリコンとも呼ばれます。
他の太陽光電池と比べて薄く、軽量なため設置制限がある場所に適しています。
また、利用される素材が安価で製造工程も簡単なため、とても安価になります。
一方で発電効率は低く、高温多湿環境に弱いため、日本での利用が難しいという特徴があります。
最近はアモルファスシリコンと他の太陽光電池を組み合わせることで発電効率や安定性を高める手法なども増えてきています。
参考までに以下、比較表になります。
| シリコンの種類 | 単結晶 | 多結晶 | 微結晶 | 非晶質 |
| 発電効率 | ◎ | 〇 | 〇 | ✕ |
| 価格 | ✕ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 用途 | 産業用 | 産業用/住宅用 | 産業用 | – |
化合物系
化合物系太陽光電池は、変換効率が高く、比較的低いコストで製造できるため、太陽光発電産業で注目を集めている太陽光電池になります。
尚、化合系太陽光電池は主にCISとCIGSとCdTeの2種類に分類されます。
①CIS
CIGS太陽光電池は銅(Cu)、インジウム(In)、セレン(Se)から構成される太陽光パネルになります。
熱や湿気に対する安定性が高いため、ホットスポットが発生しにくい特徴があります。
また、有害な物質を含んでいないため、環境に対する影響が少なく、エコロジカルな発電システムとして注目を集めています。
ただし、現在のCIS太陽光電池の効率は、一部の結晶シリコン太陽電池や化合物系太陽光電池に比べて低いため、今後の研究開発が求められています。
②CIGS
CIGS太陽光電池は銅(Cu)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)から構成される太陽光電池になります。
変換効率が高く、柔軟性も高いため、曲面に取り付けることも可能となります。
また、低光照度下でも高い発電性能を発揮できます。
製造コストも半導体素材を直接基盤に堆積することで、製造コストを低減できるため、今後の普及が期待されています。
③CdTe
CdTe太陽光電池は、カドミウムテルライト (CdTe) と呼ばれる半導体薄膜を使用して太陽光を電力に変換する薄膜型太陽光電池になります。
CdTeは熱や湿気に対する安定性が高いため、ホットスポットが発生しにくいという特徴があります。
また、有害な物質を含んでいないため、環境に対する影響が少なく、エコロジカルな太陽光電池として注目を集めています。
その他、CdTeの薄膜は長期間の使用によって劣化する可能性があるため、寿命が短いといわれています。
また、高い変換効率を実現するには微妙な材料制御が必要で、技術的な課題もあります。
有機系
有機系太陽光電池は有機半導体を利用した太陽光電池になります。
有機系太陽光パネルは柔軟性があり、曲げやすいため様々な曲面形状にすることができる他、経年劣化が少なく長期間の利用が可能となります。
また、製造も比較的簡単なため、他の太陽光電池と比べて低コストで製造ができます。
一方で電気伝導度が低いため、発電効率が悪く効率的に変換することが難しいとされています。
また、熱に弱いため高温環境下では劣化が進みやすいため、使用環境も限定されます。
量子ドット系
量子ドット系太陽光電池はナノメートルサイズの量子ドットを利用した太陽光パネルになります。
量子ドット太陽光電池は他の太陽光電池に比べて、電力を効率的に変換できるため、高い変換効率が期待されています。
また、量子ドットはナノレベルの微小なサイズで作られているため、薄型の太陽光電池を作ることができます。
そのため、柔軟性があり、曲げやすいため、様々な曲面形状にすることができる他、経年劣化が少なく長期間の利用が可能となります。
一方で量子ドットを作るには高度な製造技術が必要なため、製造コストが高く、技術開発が必要とされています。
まとめ
今回は太陽光パネルの素材である太陽光電池について説明させて頂きました。
太陽光パネルを選ぶ際は、出力や耐久性や変換効率などが重要になります。
長期間運用する場合は、耐久性や変換効率が高い太陽光電池を利用した太陽光パネルを選ぶことをおすすめします。
久野商事ではフェンスや防草シートだけでなく、太陽光パネルなどの太陽光発電資材も取り扱っております。また、取付工事もお請けしておりますので、材料購入から工事まで一貫してご対応が可能となります。
材料や工事についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。









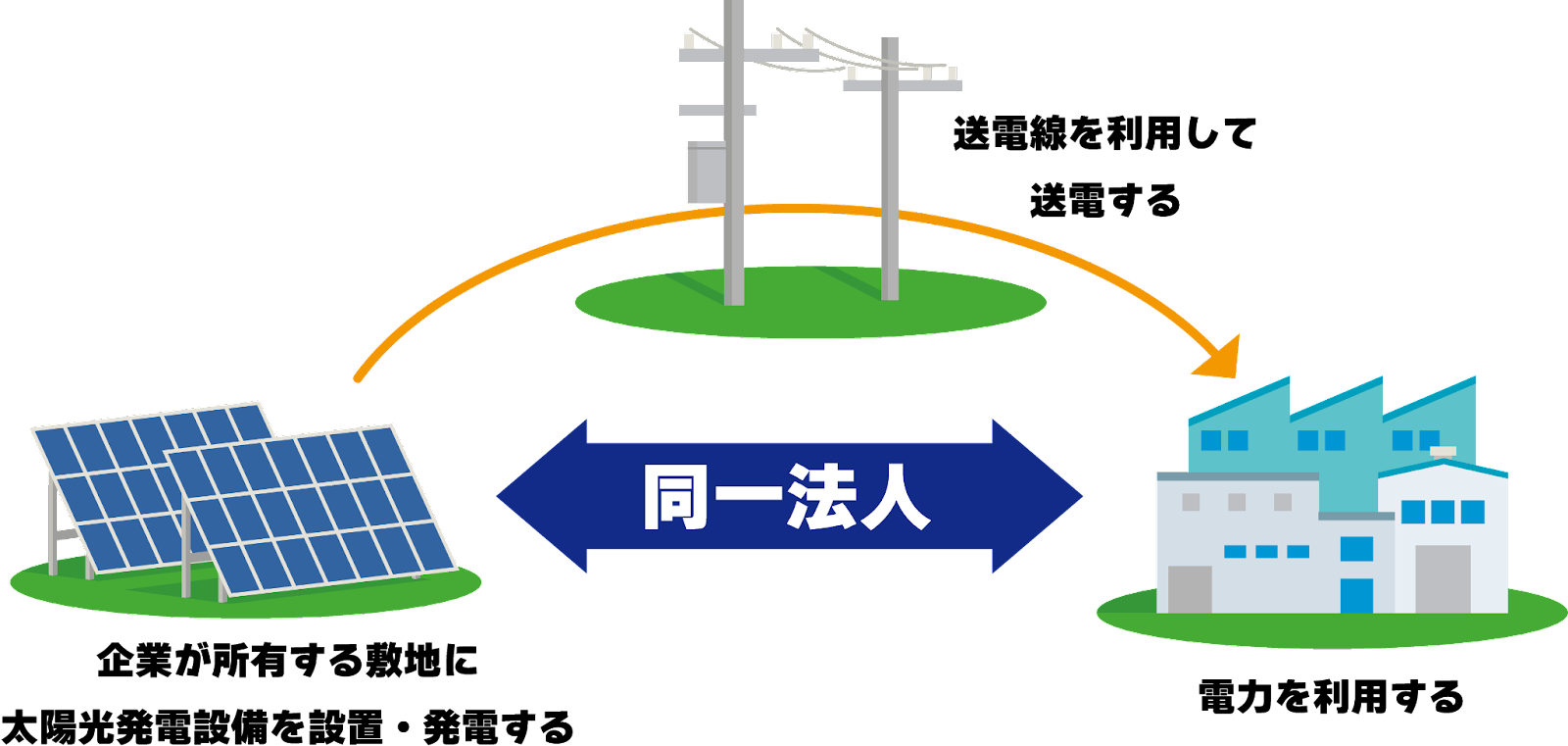
 カーボンニュートラルについて徹…
カーボンニュートラルについて徹…